
『源氏物語』「若紫との出会い」の現代語訳と重要な品詞の解説1
平安時代中期の長編物語『源氏物語』の光源氏と若紫との出会いの場面の現代語訳と品詞分解を解説しています。「九月ばかりに」から「けしきあり。」までの文章です。
黄表紙風の古典学習サイト

平安時代中期の長編物語『源氏物語』の光源氏と若紫との出会いの場面の現代語訳と品詞分解を解説しています。「九月ばかりに」から「けしきあり。」までの文章です。

平安時代中期の日記『蜻蛉日記』の「うつろひたる菊」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「つとめて」から「限りなきや。」までの文章です。

平安時代中期の日記『蜻蛉日記』の「うつろひたる菊」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「これより」から「ものしたり。」までの文章です。

平安時代中期の日記『蜻蛉日記』の「うつろひたる菊」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「九月ばかりに」から「けしきあり。」までの文章です。

鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』の「唐に卒塔婆血つくこと」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「これを見て」から「なりかし。」までの文章です。

鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』の「唐に卒塔婆血つくこと」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「この男ども」から「里移りしぬ。」までの文章です。

鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』の「唐に卒塔婆血つくこと」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「おのれが親」から「下りにけり。」までの文章です。

鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』の「唐に卒塔婆血つくこと」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「この女は」から「と問へば、」までの文章です。

鎌倉時代前期の説話集『宇治拾遺物語』の「唐に卒塔婆血つくこと」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「昔、唐に」から「見えにけり。」までの文章です。
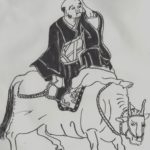
江戸時代前期の俳諧紀行文『笈の小文』の「造化にしたがひ造化にかへれ」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「西行の和歌」から「もてなす。」までの文章です。