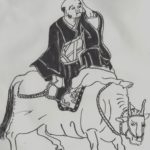
『笈の小文』「造化にしたがひ造化にかへれ」の現代語訳と重要な品詞の解説1
江戸時代前期の俳諧紀行文『笈の小文』の「造化にしたがひ造化にかへれ」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「百骸九竅」から「つながる。」までの文章です。
黄表紙風の古典学習サイト
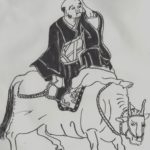
江戸時代前期の俳諧紀行文『笈の小文』の「造化にしたがひ造化にかへれ」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「百骸九竅」から「つながる。」までの文章です。

平安時代中期の日記『更級日記』の「猫・大納言殿の姫君」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「その後は」から「聞き知り顔にあはれなり。」までの文章です。

平安時代中期の日記『更級日記』の「猫・大納言殿の姫君」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「わづらふ姉」から「いみじくあはれなり。」までの文章です。

平安時代中期の日記『更級日記』の「猫・大納言殿の姫君」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「花の咲き散る」から「思ひてあるに、」までの文章です。

奈良時代の歴史書『古事記』の「海幸山幸」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「かれ、各」から「仕へまつるなり。」までの文章です。

奈良時代の歴史書『古事記』の「海幸山幸」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「ここをもちて」から「奏さむ。』と言ひき。」までの文章です。

奈良時代の歴史書『古事記』の「海幸山幸」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「ここに海の神」から「語りたまひき。」までの文章です。

奈良時代の歴史書『古事記』の「海幸山幸」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「ここに火遠理命」から「人あり。』とまをしき。」までの文章です。

奈良時代の歴史書『古事記』の「海幸山幸」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「ここに塩椎神」から「あやしと思ひき。」までの文章です。

室町時代前期の能役者・能作者の世阿弥の能楽論書『風姿花伝』の「因果の花」の現代語訳と重要な箇所の品詞分解を解説しています。「この男時」から「徳あるべし。」までの文章です。